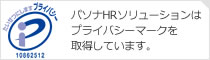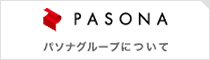いつもの競争相手もピンチのときには仲間
「仕事絡みでの恐ろしかった思い出」と申しましても、商社での仕事なので、生命に関わるほど危険な目にあったわけではありません。その辺りはあらかじめお含みおき願います。
日常業務での具体例ですが、船積み期限に貨物が到着せず危うく積み残しそうになったり、売値の計算を間違えて大損を被りそうになったり、言葉の行き違いで重要客先を怒らせてしまったりなどなど、冷汗をかいたことは数えきれません。しかしながら、その都度、上司や先輩・同僚達から「救いの手」が差し伸べられ、幸い大事に至らず切り抜けることができました。「渡る世間に鬼はなし」とか「地獄で仏」のことわざを実感したものです。当社には「社内といえども周りは全員競争相手」のごとき厳しい雰囲気があった一方、いざというときには全社が一体となって難局に対応する強固なチームワークが存在したと記憶します。
アブダビの法廷に立つことに…、その理由とは
前置きが長くなってしまいましたが、私にとって「忘れ得ぬ体験」をご披露いたします。1970年代、建設景気に沸く中近東各地向けに世界各国からのセメント輸出がブームでした。ご多分にもれず当社でも国内セメントメーカー各社を総動員して、中近東のSAUDI ARABIA,UAE,KUWAITなどの需要地向けにセメントおよびクリンカーの船積みに忙殺されておりました。現地のアラビア湾にはセメントを満載した船舶が荷揚げ待ちの状態で多数滞船し大混雑状態でした。各船舶にはそれぞれ荷揚げ所要期間として一定の日限がありますが、船混みなどでこの日限内での荷揚げが完了できない場合、荷受人(バイヤー)は船会社から「滞船料」(略称:デマ)を請求されます。この辺りの詳しい説明については今回の限られた紙面では不可能ゆえ、別途専門家にご質問くだされば幸甚です。
中途の経緯は省略しますが、荷受人が上記デマの支払いに容易に応じぬため、船会社に代わり当社が(用船者)が荷受人を相手取り、現地ABU DHABIの裁判所に「デマ請求」の告訴するに至りました。現地に出張した私は「原告」代表として法廷に召喚されました。本社から同行した法務部担当者(中近東の専門家)は陪席を許されず、現地人弁護士(アラビア人)が立ち会ってくれましたが、誠に心細い限りでした。
緊張の「法廷で虚偽の証言をしたならば即時に収監する」という言葉
狭い法廷で起立した私に対して裁判官から種々質問がなされました。アラビア語ですから全く意味不明です。判事席の傍らに座を占める黒人通訳(エチオピア人の由)が裁判官の質問を英訳してくれるので、おおよその意味は把握できましたが、念のため「もう一度お願いします」と懇請し確認したものです。裁判官への返答は、「YES(はい)」または「NO(いいえ)」のいずれかのみ。そのほかの余計な説明は許されませんでした。裁判官からは冒頭に「もし、お前がこの法廷で虚偽の証言をしたならば即時に収監する」と告知され肝が縮みました。中近東の監獄とは、とても恐ろしい場所であることはすでに聞きおよんでおりました。
ようやく小一時間ほどの裁判官とのやりとりが終了。「退廷してよろしい」とのことで、入廷前に没収されていた私のパスポートを裁判官がポイと投げ返してくれたときには、体中の力が抜け、文字通り「緊張の糸が切れた」ような状態になりました。判事席の後方に窓があり青い海原が望めることがわかり、この法廷が海に面していたことを、そのときになり初めて気がつきました。「収監されずに解放されてよかった」と痛感しました。帰国後も法廷での模様を時折夢でみたものでした。裁判自体は被告(荷受人)が間もなく死亡してしまったため「デマ回収」は不能となり、船会社へは当社が弁済し損金処理したと記憶します。ちなみに、当社社員で中近東の法廷に召喚され、証言した例はまれのことと、後日社内で側聞しました。
灼熱の中近東へ出張し、駆けまわっていた「若き日々」を思い出し感慨無量です。
※本記事は匿名とさせていただきます。